海洋散骨の需要は高まっている!その背景や今後の海洋散骨需要の展望を解説

近年、海洋散骨は従来のお墓に代わる新しい供養の選択肢として関心を集めています。
「お墓を持たずに故人を自然に還したい」と願う人が増えており、海洋散骨の需要は年々拡大傾向にあるのです。
また、近年では身近な家族や親しい友人だけで見送る家族葬が広がっており、「規模を小さく、負担を減らしてシンプルに供養したい」というニーズが高まっています。
こうした流れとも重なり、海洋散骨は自然志向や負担軽減の面で注目され、多くの人が選び始めていいます。
本記事では、海洋散骨の需要が高まる背景や現状、利用者層の特徴、地域ごとの傾向、そして今後の展望について解説します。
海洋散骨の需要は年々高まっている!

かつて海洋散骨はごく一部の人々が選ぶ特殊な葬送法でしたが、近年では一般的な選択肢の一つとして広く認知されるようになりました。
専門の散骨業者や葬儀社がサービスを拡充していることからも、その需要の高まりを読み取ることができます。
実際、一般社団法人日本海洋散骨協会の統計によれば、同協会加盟企業による散骨施行件数は2018年の約1,049件から2021年には1,709件へと増加。
さらに、同協会の調査では2024年度に3,000件を突破し、わずか数年で約3倍に拡大したことが明らかになっています。
従来のお墓に縛られない自由な供養を求める人が増えていることが、こうした需要の急成長を裏付けています。
また、テレビや雑誌などの各種メディアで取り上げられる機会が増え、実際に散骨を体験した人々の口コミが広がったことも需要が高まった要因の1つでしょう。
「海洋散骨は安心できる供養方法」という認識が社会に浸透しつつあるのです。
法的な観点からも、節度を守った方法で行う限り違法性はないことが周知され、社会的にも正当な葬送の一形態として受け入れられ始めました。
こうした知名度と信頼性の向上を背景に、「自分も海洋散骨を検討したい」と考える人が増え、さらなる需要拡大を後押ししています。
加えて、一般社団法人日本海洋散骨協会の公式発表によれば、加盟業者数も年々増加し、2025年時点で正会員は53社に達しました。
サービス提供者の裾野が広がっている点も、業界全体の成長を象徴しています。
海洋散骨の需要が注目される背景

海洋散骨が広がる背景には、社会構造の変化と人々の価値観の多様化があります。
実際に、全国石製品協同組合が40代以上の男女1,000名を対象に行った「新しい供養のかたち(樹木葬、海洋散骨、デジタル墓)についてのアンケート調査」によれば、海洋散骨を利用したいと考えている方の割合は全体の40.8%となっています。
4割を超える人々が現実的な選択肢として受け止めていることは、従来の墓地中心の供養観が大きく揺らぎ始めている証拠といえるでしょう。
つまり海洋散骨は「特殊な方法」ではなく、もはや相当数の人が選択肢として視野に入れる“新しいスタンダード”になりつつあるのです。
この背景には以下の要因が大きく影響しています。
- 少子高齢化によるお墓の承継者不足
- 墓地不足による維持管理コストの増加
- 自然志向・宗教観のフリー化に伴う価値観の広がり
これらの社会的要因が複雑に絡み合うことで、「お墓を持つのが当然」という固定観念は少しずつ薄れ、結果として海洋散骨の需要が一層高まっているのです。
それぞれの要因を詳しく見てみましょう。
少子高齢化によるお墓の承継者不足
日本社会の少子高齢化により、家のお墓を受け継ぐ人がいない家庭が増えています。
実際、第一生命保険株式会社が2010年7月に公表した、「35 歳から 79 歳までの全国の男女 600 名に聞いた『お墓のゆくえ-継承問題と新しいお墓のあり方-』」によれば、お墓が将来無縁化すると考える人の数は全体の54.4%(「いつかは無縁墓になる」:50.3%、「近いうちに無縁墓になる」:4.1%)と5割以上にのぼっています。
2010年時点でこの結果なので、15年を経て少子高齢化がさらに進んだ現在はさらにその傾向が強まっていると考えるのが自然でしょう。
実際に、子どもがいなかったり遠方に住んでいたりするために「先祖代々のお墓を守れない」というケースは、もはや珍しい話ではありません。
加えて、子や孫に負担をかけたくないと願う高齢者も増えており、自分の代でお墓を終わらせようとする動きが顕在化しています。
こうしたお墓の継承者不在問題を解決する手段として、海洋散骨を選ぶ人が増えているのです。
実際、大手散骨業者のアンケート調査などでも「お墓を残さない」「子どもの負担を軽減したい」ことを理由に散骨を検討する人が一定数いることが明らかになっています。
みらい散骨にご依頼されるご遺族さまの中にもそういった理由で海洋散骨を検討されたという方は多くいらっしゃいます。
継ぐ人がいなくても遺骨を自然へと還せる海洋散骨は、無縁墓(承継者のいない墓)の増加を防ぐ有効な手段として、今後ますます注目されていくでしょう。

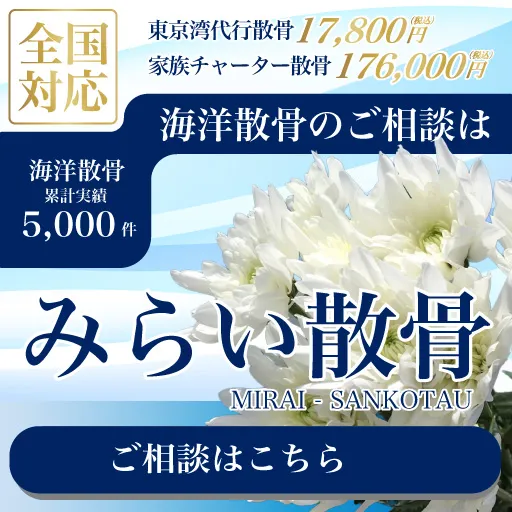
墓地不足による維持管理コストの増加
都市部では墓地の不足や価格高騰が深刻な問題となっています。
都心の人気霊園では、募集区画に対して数十倍もの応募が殺到し、抽選を勝ち抜かない限り取得できないほどの狭き門です。
墓地の使用料や墓石代も年々高騰しており、一般家庭にとって大きな負担と言わざるを得ません。
一方、地方でも安心はできません。
核家族化や人口減少の影響で墓守を担う人が減り、結果として墓の荒廃や無縁墓の増加といった課題が顕在化しています。
加えて、お墓を建てれば墓石代や永代使用料に加え、毎年の管理費がかかり続けます。
生涯にわたる経済的負担は決して小さくありません。
その点、海洋代行散骨の費用は一般的に2万~3万円程度が相場とされ、平均150万円以上を要する従来のお墓と比べて圧倒的に低コストです。
さらに散骨後には管理費や墓掃除といった維持管理の手間が不要なため、「お墓を持たないことで経済的にも時間的にも負担を軽減できる」という点が大きな支持を集めています。
都市部で高額な墓地を確保するのが難しい方にとってはもちろん、「墓じまい」を検討する家族にとっても、海洋散骨は現実的で合理的な選択肢となりつつあるのです。
自然志向・宗教観のフリー化に伴う価値観の広がり
現代において、葬送に対する価値観は大きく多様化しています。
形式にとらわれず「自分らしい最期」を望む人や、「死後は自然に還りたい」と考える自然志向の人が増えてきました。
従来のように菩提寺にお墓を構え、手厚く供養するという宗教的慣習に縛られるのではなく、「個人の生き方や信条を尊重した自由な弔いを選びたい」という風潮が広がっているのです。
そのニーズに応える供養方法のひとつが、海洋散骨です。
海洋散骨が選ばれる理由としては、「お墓を持たずに自然へ還れるという開放感」や「宗教色のないシンプルな儀式であること」が挙げられます。
実際、株式会社ハウスボートクラブが2024年に20代~70代の1,152名を対象に実施した「お墓の希望・海洋散骨に関する意識調査」では、海洋散骨に対して最も多かった印象が「管理の手間がない」(34.3%)、続いて「自然に還れる」(33.1%)という結果でした。
否定的な意見よりも肯定的な受け止め方をする人の方が多いことがわかります。
さらに、海洋散骨は特定の寺院や宗派に依存せず行えるため、無宗教の方でも選びやすい供養方法です。
故人の希望を尊重しやすい点も、大きな支持を集める理由といえるでしょう。
海洋散骨の需要がある利用者層

海洋散骨の需要拡大には、特定の利用者層のニーズが大きく関係しています。
特に高齢層(団塊世代)や都市部の居住者、そして海に特別な思いを持つ人々が中心的な存在となっています。
それぞれの層がなぜ海洋散骨を選ぶのか、背景を見ていきましょう。
団塊世代を中心とした高齢層
日本の団塊世代(1947~49年生まれ)は、2025年には全員が75歳以上となり、自らの終末期について真剣に考える時期に入りました。
この世代を中心に「子に後を託さない供養」を望む声が強く、生前からお墓ではなく散骨を選択するケースが増えています。
団塊世代の多くは自分の親の墓じまいを経験しており、「自分の代で墓を持たないことで子どもに負担を残さないようにしたい」という価値観を持つ傾向があります。
「自分の葬送方法を元気なうちに決めておきたい」という終活意識の高まりもあり、団塊世代が率先して海洋散骨を選んでいる状況です。
子や孫に経済的・精神的な負担を残さず、自然に還ることのできる散骨は、この世代にとって理想的な「自分らしい最期の迎え方」として映っているのでしょう。
都市部在住者
都市部に暮らす人々の間でも、海洋散骨の需要は着実に高まっています。
都市圏では前述の通り、墓地不足や価格高騰が顕著であり、お墓を手に入れて維持することは地方に比べて格段に難しいのが現実です。
さらに、核家族化が進んだ結果、実家のお墓から離れて暮らす人が増え、将来的に墓守を担える親族がいないケースも決して少なくありません。
こうした背景から、「最初からお墓を持たない」という選択肢として海洋散骨を選ぶ都市住民が増えているのです。
株式会社鎌倉新書が2025年に実施した「第16回 お墓の消費者全国実態調査」によれば、一般墓の平均購入額は155.7万円、納骨堂は79.3万円、樹木葬は67.8万円という結果が示されています。
それに比べ、代行散骨の費用は2万~3万円程度と大幅に抑えられ、コスト面でのメリットが大きいと言えます。
さらに、都心から近い東京湾で散骨を行えるサービスも多く、アクセスの利便性や価格面から見ても現実的な選択肢となっています。
実際、みらい散骨では東京湾での代行散骨プランなら17,800円(税込)~、チャーター散骨でも176,000円(税込)~から利用可能であり、都内に墓地を構えるよりも遺族の経済的負担を大きく軽減できます。
都市住民にとって、遠方に墓を建てて将来の維持管理に不安を抱えるよりも、身近で手軽に行える海洋散骨のほうが合理的だと考える人が増えてきたのではないでしょうか。
加えて、「墓じまい」を行い、自宅での手元供養やオンラインで故人を偲ぶといった新しい供養スタイルを取り入れる家族も少なくありません。
その中心に位置しているのが、海洋散骨という新しい選択肢なのです。
海に思い入れのある人
漁業関係者やマリンスポーツ愛好者など、海と深い関わりを持つ人々の間では、「自分らしい最期」として海洋散骨を望む傾向が見られます。
生前から海を愛してきた人にとって、「自分の遺骨も愛した海へ還してほしい」という願いはごく自然な発想でしょう。
たとえば「大好きだった海で眠りたい」という故人の遺志を叶える手段として、海洋散骨は最も適した方法のひとつと考えられています。
実際に、生前からその希望を公言する人も少なくありません。
元東京都知事の故・石原慎太郎氏が、生前より海への散骨を望んでおり、亡くなった後に葉山町沖で散骨されたことは、大々的にニュースに取り上げられたこともあり、多くの人の記憶に残っているのではないでしょうか。
海辺の町で育った人、海軍や商船に携わった人、あるいはサーフィンやダイビングを趣味とした人など、人生の思い出が海と結びついている人ほど、海洋散骨への関心は強まる傾向にあります。
それは単にロマンチックな願望にとどまらず、「自分のルーツや魂を海に返したい」という深い哲学的な思いでもあるのです。
さらに、ご遺族にとっても故人が愛した海を訪れることで、いつでも思い出を偲ぶことができるという大きな慰めとなります。
海洋散骨は、亡き人と遺された人の心をつなぐ拠り所ともなり得る供養の形だと言えるでしょう。
今後の海洋散骨需要の展望

海洋散骨の需要は、今後さらに拡大していくと見込まれています。
その背景には次の3つの要素があります。
- お墓問題の深刻化によって需要が広がる
- 法規制やガイドライン整備でより安心感が持たれる
- オンライン法要やデジタル供養など新サービスが登場する
それぞれくわしく見ていきましょう。
お墓問題の深刻化によって需要が広がる
少子高齢化が一層進み、今後亡くなる人の数は増加の一途をたどります。
一方で、遺されたお墓を管理・継承する人がいない無縁墓や、墓所が荒廃したまま放置されるケースも増えていくでしょう。
無縁墓となって行政が遺骨を改葬する件数も増えていますが、そうなる前に最初から墓を作らず散骨するというニーズが広がる可能性が十分に考えられます。
現に、「自分のお墓はいらないから散骨してほしい」と遺言する高齢者も増えており、新たなサービス展開を模索している葬儀社や石材店もいます。
社会全体で「墓を持たない」ライフスタイルが市民権を得ていけば、海洋散骨の需要は今後さらに広がっていくでしょう。
法規制やガイドライン整備でより安心感が持たれる
一昔前まで、散骨には「法的なグレーゾーンがあるのでは」という不安が一部にありました。
しかし近年では国や自治体、業界団体によるガイドライン整備が進み、適切な手続きのもとで行われる散骨は安心して利用できるようになっています。
厚生労働省は2020年3月、「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」を取りまとめ、関係者の宗教的感情や公衆衛生に配慮した散骨の基準を示しました。
散骨業者はガイドラインに沿った運用を行うことで利用者に安全・安心を提供できる体制が整いつつあります。
もともと日本の法律上、散骨を明確に禁止する規定はなく、節度をもって葬送の一環として行われる限り違法ではないことが法務省見解で示されています。
(2)散骨は、原則として自由に行える
散骨は、墓地、埋葬等に関する法律にこれを禁止する規定はなく、一部地域の条例を除いて法規制の対象外とされています。
また、散骨については、法務省が、1991年に、葬送のための祭祀として節度をもって行われる限り遺骨遺棄罪(刑法190条)に違反しないとの見解を示しています。
このように、散骨は「節度をもって行われる限り」自由に行うことができます。
つまり「墓地埋葬法」にも抵触せず、刑法上の遺骨遺棄罪にも当たらない範囲であれば散骨は自由に行えるのです。
オンライン法要やデジタル供養など新サービスが登場する
海洋散骨の普及に伴い、従来のお墓参りに代わる新しい供養サービスも登場しています。
散骨の場合、物理的なお墓が残らないため「故人を偲ぶ場がないのでは」と心配する声がありますが、近年は技術の力でそうした課題をカバーする試みが広がっています。
一つはオンライン法要・リモート散骨セレモニーです。
たとえば、一部の海洋散骨業者は、散骨船に乗船できない遠方の親族のためにZoomを活用したオンライン海洋散骨法要を提供しています。
参加者全員がインターネットで繋がり、リアルタイムで散骨の航海に「仮想同行」し、散骨ポイントに着いたら故人の名前を読み上げて花を捧げ、お経を流すという流れです。
離れていてもデジタル空間を通じて故人を送り出す体験を共有できるサービスは、コロナ禍で注目されたリモート葬儀をきっかけとして、今後需要が高まるでしょう。
さらにVR技術で海中や空から故人を偲ぶバーチャル供養など、テクノロジーを駆使した新サービスの開発も期待されています。
こうしたライフスタイルの変化に合わせた供養の多様化に伴い、海洋散骨の需要も今以上に高まってくることが予測できます。
海洋散骨の需要は今後も高まっていく可能性が高い

海洋散骨の広がりは、社会の変化と人々の価値観の多様化に支えられています。
少子高齢化によるお墓の継承問題や、経済的な負担への不安、そして自然志向や自分らしい供養を求める気持ちが、新しい供養の形としての散骨を後押ししてきました。
実際に、散骨件数は年々増え、認知度も高まっており、その需要が拡大しているのは明らかです。
今後も高齢化が進むなかで無縁墓の問題が深刻化し、公営墓地の整備が追いつかない状況が予想されます。そうなれば「お墓を持たない供養」を選ぶ人はさらに増えていくでしょう。
「みらい散骨」では、東京湾での代行海洋散骨を17,800円(税込)~という国内最安値帯の価格でご案内しています。
また、ご家族だけでゆったりと見送れるチャーター散骨プランも用意しており、東京湾エリア(ディズニーランド沖・羽田沖)で176,000円(税込)〜というリーズナブルな価格で貸切船をご利用いただけます。
海洋散骨をご検討されている方はぜひ、お気軽にご相談ください。

