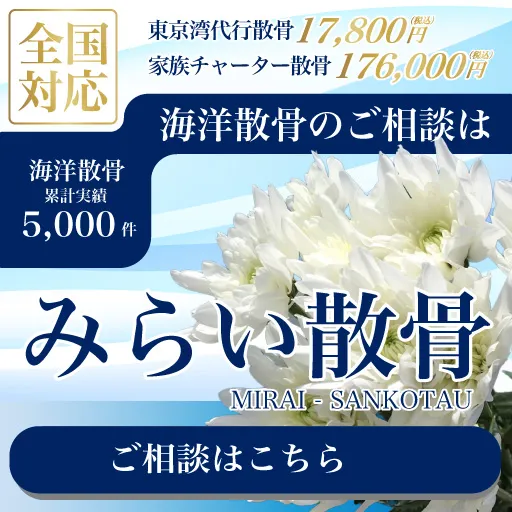海洋散骨の手続きガイド|流れ・必要書類・注意点を徹底解説
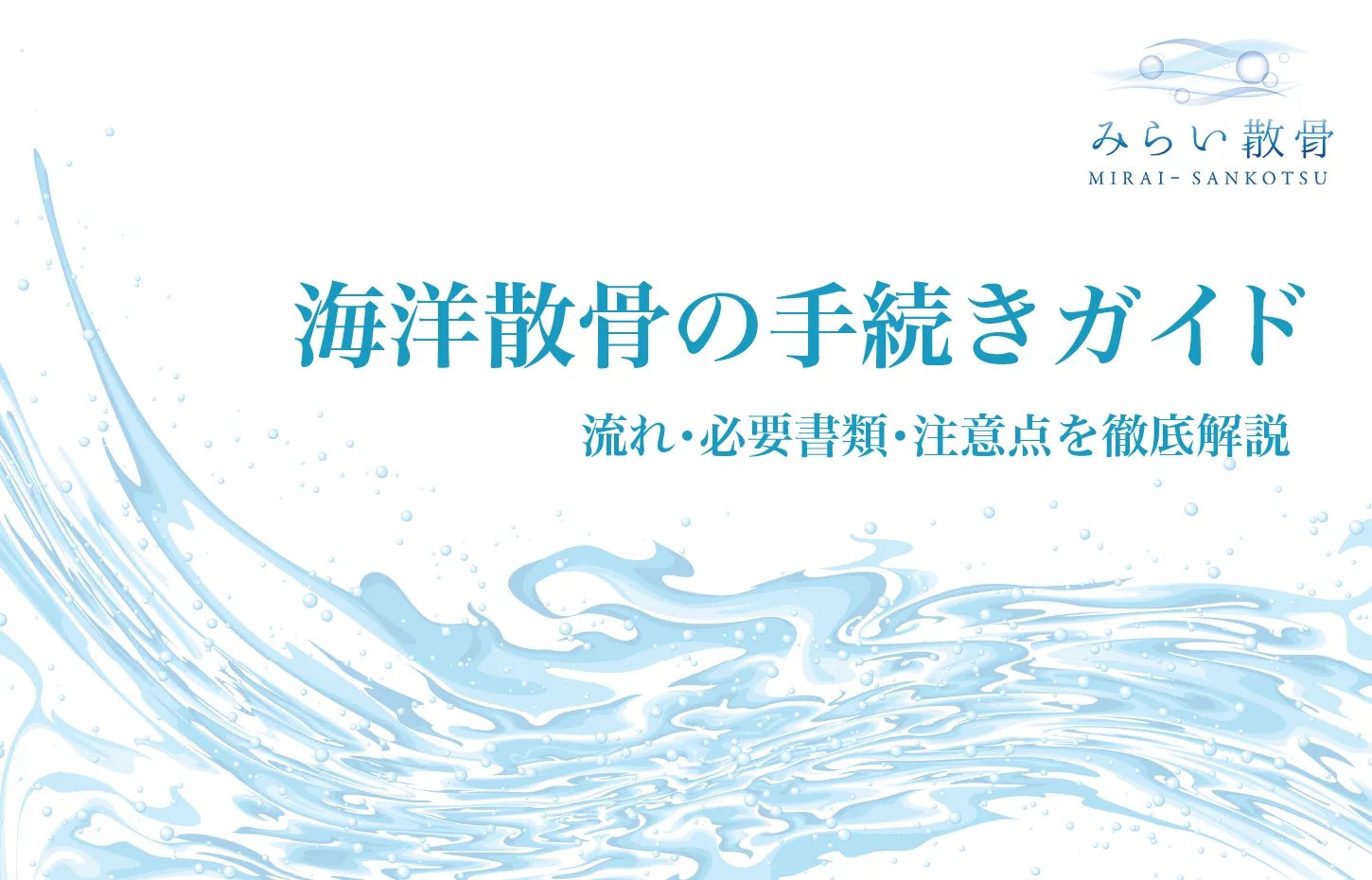
海洋散骨とは、故人の遺骨をお墓や霊園などに埋葬するのではなく、海に撒く葬送方法です。近年の「死後は自然に還りたい」という個人の希望や、「お墓を作っても維持管理ができない」という遺族の価値観に合っていることから注目されています。
また、宗教や形式にとらわれない自由な葬送方法であることも評価されているポイントです。
しかし、海洋散骨に関する情報は限られているため、「どんな手続きが必要なのか」「法律に反することはないのか」「どんな書類が必要なのか」が分からないということも少なくありません。
この記事では、海洋散骨の手続きを知りたいという方に向けて、海洋散骨の基本的な流れや必要な書類と準備事項、注意点、よくある質問への回答などについて分かりやすく解説します。
海洋散骨を行うには法律上の手続きが必要?

日本では海洋散骨を直接禁止・規制する法律は存在しませんが、火葬や改葬の許可証の取得など、遺骨の取り扱いには一定の手続きが必要です。
たとえば、刑法190条では「遺骨遺棄罪」が定められていますが、この法律では遺骨を不法に投棄したり、故意に放置したりすることを禁じたものなので、海洋散骨は該当しません。
しかしながら、海洋散骨については、法務省が1991年に「葬送のための祭祀として、節度を持って行われる限り、遺棄罪には当たらない」という見解を示しています。
この見解は「遺骨と分かる大きさのまま散骨をしてはならない」ということと解釈されています。
また、厚労省の「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」には「焼骨は、形状が視認できないよう粉末化(粉骨)すること」と明記されており、一般的に2mm以下に粉骨するのが通例です。
法務省の見解や厚労省のガイドラインに基づき、海洋散骨をする際には事前に、見た目で人骨と分からないように2mm以下のパウダー状にする粉骨処理が必要になります。
また、法律ではありませんが、次の2つの自治体では海洋散骨に関する条例を定めて規制を行っているので、このエリアで海洋散骨する場合は抵触しないように注意が必要です。
| 自治体名 |
規制内容 |
|---|---|
| 静岡県熱海市 | 土地から10km以上離れた海上で散骨すること |
| 静岡県伊東市 | 陸地から11.11km以内での散骨を禁止する |
その他のエリアにおいては、条件を満たしていれば合法的に海洋散骨を行うことができます。
- 遺骨は必ず粉骨処理をする
- 沿岸から一定距離以上離れた沖合の海域で行う
- 他人に迷惑をかけないよう配慮する
- 漁場や養殖場・観光地・河川・湖沼などを避ける
- 副葬品は海に還るもののみ撒く(※海洋汚染防止の観点から、還元性のある素材に限定することが望ましい)
海洋散骨の手続きと全体の流れ

では、海洋散骨の具体的な手続きと全体の流れはどのようになっているのでしょうか?
ここでは、一般的な手続きの流れを次の5つのステップに分けて説明します。
- ステップ1:散骨業者を選定する
- ステップ2:プラン内容の確認と契約手続きを行う
- ステップ3:粉骨を行う
- ステップ4:指定した日時に散骨を行う
- ステップ5:散骨証明書や記録を受け取る
以下で、それぞれについて見ていきましょう。
ステップ1:散骨業者を選定する
まず最初に、海洋散骨の専門業者を選定する必要があります。
Web検索をすると多くの業者が見つかりますが、選定に際しては次の点について確認し、自分や家族の希望に合った業者を選ぶようにしましょう。
- 散骨可能なエリア・海域
- 散骨プランの種類や費用
- 過去の散骨実績や口コミ
- 散骨証明書や記録を発行してくれるかどうか
- 粉骨処理を行ってくれるかどうか
無料相談を実施している散骨業者も多いため、まずは気軽に問い合わせてみることをおすすめします。
ステップ2:プラン内容の確認と契約手続きを行う
散骨業者が決まったら、散骨プランの内容を具体的に確認して、正式な契約を結びます。
一般的に、次の3つのプランが用意されているので、故人や遺族の希望や都合などに応じて決定します。
- 貸切散骨(チャーター散骨)
- 合同散骨
- 代行散骨
散骨する海域や日程、セレモニーの有無、遺族が同行する場合は同行者の人数などによって費用が変わってきます。
また、オプションサービスとして、献花・献酒・映像記録なども依頼できます。
これらの中から自分や家族が希望する散骨方法を選んで契約手続きを行います。
その際、契約書に実施内容、料金総額・明細、支払い方法、キャンセルポリシーなどが明記されていることをしっかりと確認するようにしましょう。
ステップ3:粉骨を行う
前述のように、海洋散骨をする前には粉骨処理が必要となります。
多くの散骨業者は粉骨サービスを提供しているので、ステップ2の契約の中に含めて依頼することが一般的です。
粉骨後は専用の水溶性袋などに入れて散骨まで保管しておきます。
なお、自分で粉骨処理をすることもできますが、衛生面や心理的な負担などを考えると、散骨業者に依頼するのが安心です。
ステップ4:指定した日時に散骨を行う
海洋散骨を行う当日は、指定の日時に集合場所から出港し、散骨場所に向かいます。
散骨方法として「代理散骨」を選んだ場合は、散骨業者が代理で行います。
散骨場所に付いたら、海上で献花や黙とうなどを行うことが一般的で、宗教や慣習に合わせたセレモニーを行うこともできます。
その後、粉骨した遺骨と海に還る副葬品(花びら、お酒や飲み物、食べ物など)を海に撒きます。
なお、当日が悪天候で船が出航できない場合は延期となることがあります。
ステップ5:散骨証明書や記録を受け取る
散骨が終わると、散骨日時・海域などが記載された「散骨証明書」が発行されます。
写真や動画で記録を残してもらえるオプションを選べば、後から家族でそのときを振り返ることもできます。
証明書は、自治体やお寺に報告を求められた場合などに備えて、保管しておくと安心です。
※散骨証明書は法的義務ではありませんが、家族間の記録や後日の説明用として有効です。
海洋散骨の手続きに必要な書類

海洋散骨の手続きに必要な書類は次の通りです。
- 申込書
- 火葬許可証または埋葬許可証
- 改葬許可証(墓じまいのケース)
以下で、それぞれ見ていきましょう。
申込書
業者が指定する申込書には、故人の情報や申込者の連絡先、希望する散骨プランなどを記載します。
書式は業者によって異なっていますが、正確な情報の記入と押印が必要となります。
もし不明な点がある場合は、散骨業者に相談しながら記入するようにしましょう。
火葬許可証または埋葬許可証
海洋散骨を申し込む際には、火葬を終えたことを証明する「火葬許可証」または「埋葬許可証」の提出が必要です。
市町村役場に「死亡届」を提出する際に、「火葬(埋葬)許可申請書」を提出して交付してもらいます。
一部の自治体では、火葬と埋葬の許可を兼ねた「埋火葬許可証」を発行する場合があります。
改葬許可証(墓じまいのケース)
すでにお墓に埋葬されている遺骨を取り出して他のお墓に移す場合は、「墓地、埋葬等に関する法律」に基づき、市町村長の許可を得て改葬する必要があります。
第5条 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
引用元:墓地、埋葬等に関する法律 第5条
一方で、海洋散骨は『お墓』への再埋葬ではないため、役所では「改葬許可申請書」は法的には不要です。
ただし、墓地管理者(住職等)が遺骨を取り出す条件として改葬許可証の提出を求めるケースがあるため、散骨業者が「遺骨の受入証明(※公的書類ではありません)」を発行することで対応することもあります。
海洋散骨の手続きで気をつけたい4つの注意点
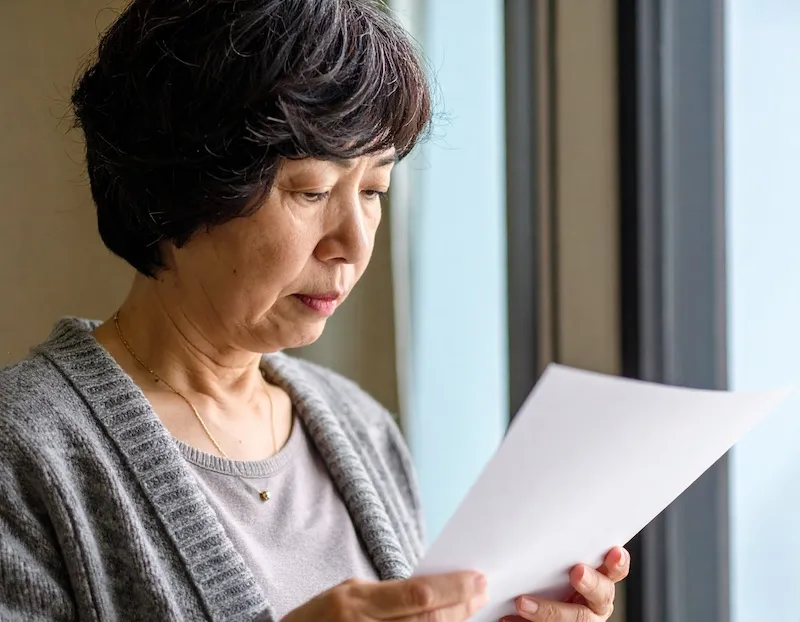
海洋散骨の手続きを行う際には、次の4つに注意するようにしましょう。
- 注意点1:家族や親族への十分な説明と合意
- 注意点2:散骨海域のルールや条例の確認
- 注意点3:宗教施設への事前相談(墓じまいのケース)
- 注意点4:遺骨の散骨処理
注意点1:家族や親族への十分な説明と合意
海洋散骨は、まだ一般に広く普及しているとはいえないため、家族や親族の間で意見が分かれることがあります。
故人が希望していたとしても、事前の説明や合意がなければトラブルのもとになりかねません。
特に年配の親族など、保守的な考えを持つ方には受け入れられにくい場合があります。
そのため、海洋散骨を選ぶ際には、家族や親族とあらかじめ話し合って合意を得ておくことが重要です。
親族の考え方や宗教、家族の関係性によっては、丁寧な配慮と時間をかけた説明が必要になるケースがあることも考えておくべきでしょう。
また、家族間で意見が分かれる可能性がある場合には、意思表示を公正証書遺言により法的に明確にしておくことで、トラブルの予防になります。
注意点2:散骨海域のルールや条例の確認
先述のように、海洋散骨に関する条例を設けて規制を行っている自治体があるほか、ルールが設けられている場合があります。
散骨業者に依頼する場合は、条例やルールに沿った対応をしてくれますが、利用者も最低限のルールやマナーを理解しておくことが必要です。
また、海洋散骨を自分で行う場合は、散骨しようと考えている海域の自治体の条例やルール、マナーなどをきちんと確認したうえで行うようにしましょう。
注意点3:宗教施設への事前相談(墓じまいのケース)
墓じまいをして海洋散骨をする場合は、これまでに遺骨を納めていたお寺や霊園に事前に相談することが必要です。
お寺の場合は、「閉眼供養」や檀家を離れることになるための「離壇料」が必要になることがあります。
必ず事前に相談し、必要な儀式や手続きを踏んでから進めるようにしましょう。
注意点4:遺骨の散骨処理
先述の通り、遺骨は必ず粉骨処理をして散骨する必要があります。
粉骨処理は自分で行うこともできますが、衛生面や心理的な負担が大きいため、専門業者に依頼することをおすすめします。
海洋散骨の手続きに関するよくある質問Q&A

ここでは、海洋散骨の手続きに関してよくある質問を2つピックアップしてみました。
- 散骨後に何か手続きをする必要はある?
- 自分で散骨する場合、特別な手続きが必要?
以下で、詳しく見ていきましょう。
散骨後に何か手続きをする必要はある?
散骨は墓地埋葬法上の「埋葬」には該当せず、散骨後に市区町村へ追加で届け出る必要はありません(戸籍や死亡届などの提出は別途必要です)。
そのため、散骨が完了した後には、特に手続きは必要ありません。
ただし、一般的には散骨業者から「散骨証明書」が発行されるので受領しておきましょう。
また、散骨時のビデオや写真を依頼していた場合も受領しておきます。
自分で散骨する場合、特別な手続きが必要?
個人で海洋散骨を行うことも可能ですが、散骨可能な海域の選定や粉骨処理、船の手配などが必要となります。
手間がかかるうえに、散骨業者に依頼する場合と同等の費用がかかることもあります。
そのため、できるだけ専門業者に依頼することをおすすめします。
心を込めた海洋散骨のために、正しい手続きを知ろう

この記事では、海洋散骨を行う際の基本的な流れや必要な書類、準備事項、注意点、よくある質問への回答などについて分かりやすく解説しました。
海洋散骨は、自然に還るという考え方に基づく、自由で新しい形の葬送方法です。
心を込めた海洋散骨をスムーズに進めるためには、正しい手続きの流れや必要な書類、注意点をしっかり把握しておくことが重要です。
「みらい散骨」では、5,000件以上の海洋散骨の実績があり、東京湾を中心とするエリアで海洋散骨を行っています。
大切な人の海洋散骨をお考えの方は、ぜひ「みらい散骨」までご相談ください。