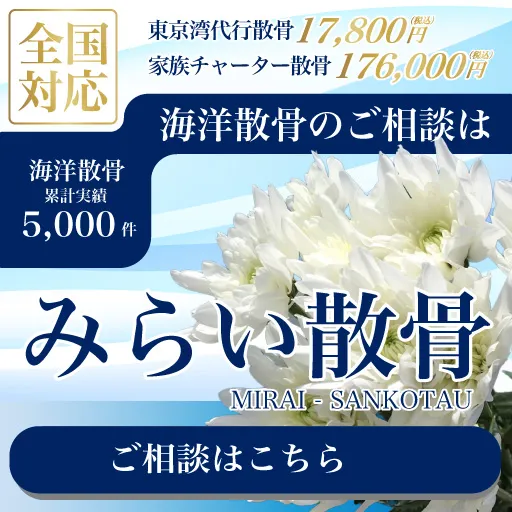海洋散骨後の法事は必要?実施方法・供養スタイル・注意点を解説
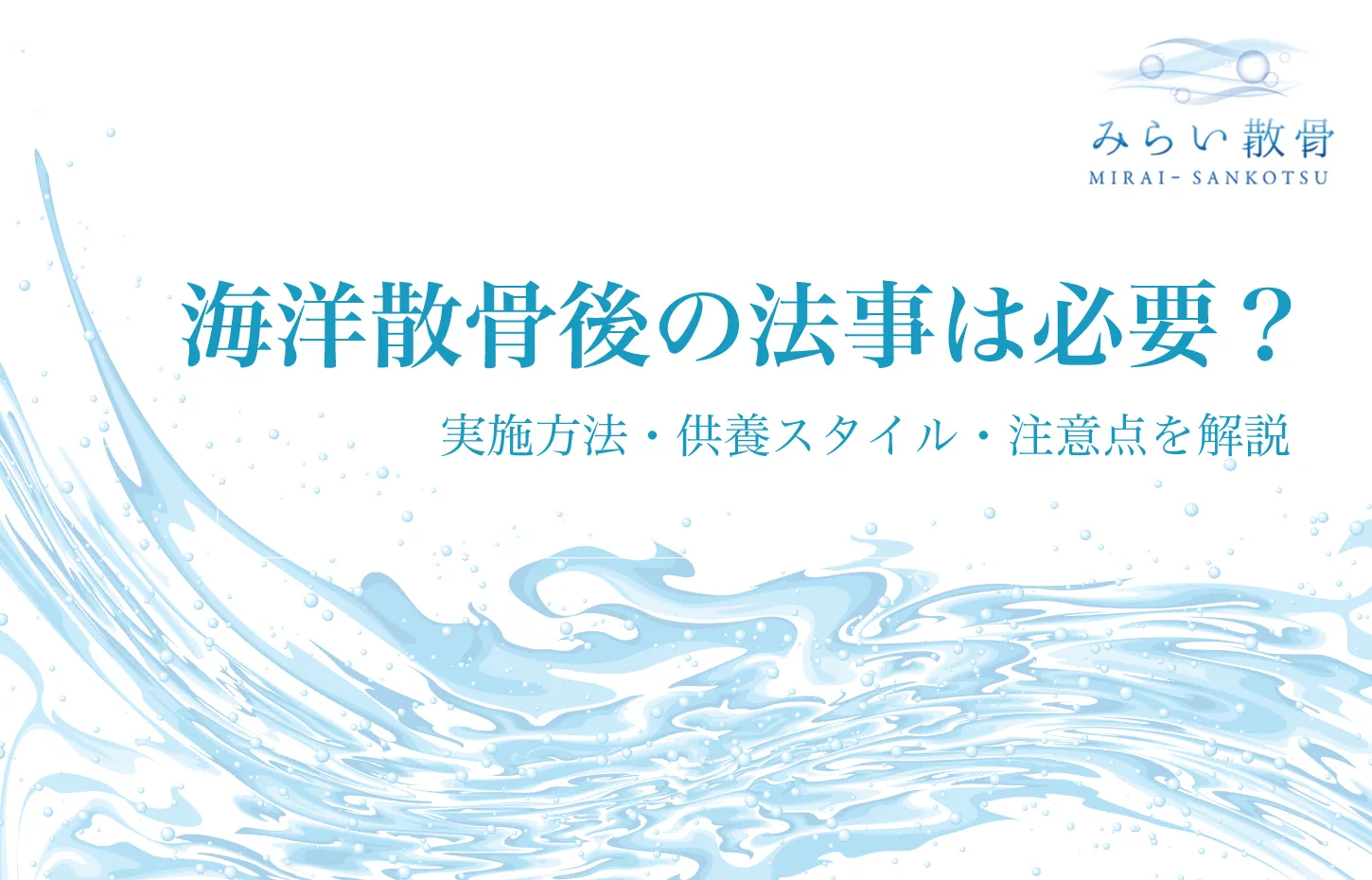 近年では、「お墓を持たずに自然に還りたい」と考える方が増えており、そのような価値観に共感する人々の間で、海洋散骨が選択肢の一つとして広まりつつあります。海洋散骨を専門に扱う業者も年々増加しており、現在では、法律やマナーに配慮しながら安心して散骨を執り行える環境が整ってきました。
近年では、「お墓を持たずに自然に還りたい」と考える方が増えており、そのような価値観に共感する人々の間で、海洋散骨が選択肢の一つとして広まりつつあります。海洋散骨を専門に扱う業者も年々増加しており、現在では、法律やマナーに配慮しながら安心して散骨を執り行える環境が整ってきました。
しかし、散骨そのものは無事に終えたものの、その後の法事について「お墓がないからどうすればよいのか分からない」「法事は必要なのだろうか」といった戸惑いや不安の声も多く聞かれます。
そもそも法事とは、故人の冥福を祈るため、一定の節目に行われる仏教の追善供養のことです。
代表的なものとして、初七日や四十九日などの「忌日法要」、一周忌・三回忌・七回忌といった「年忌法要」があります。
こうした法事は、親族やご縁のある方々が集まり、僧侶の読経を受けたり、会食の場を設けたりすることで、故人を偲び、遺された人々の心を整理する大切な儀式です。
したがって、法事はお墓の有無にかかわらず行うことができ、その本質は形にとらわれるのではなく故人を思う気持ちにあります。
この記事では、海洋散骨を終えた方やそのご遺族に向けて、散骨後の法事の必要性、供養の具体的な方法、注意点などをわかりやすく解説します。
海洋散骨後に法事は必要?

まず、次の2つの観点から海洋散骨後の法事の必要性について説明します。
- 心の区切りとして有効
- 「お墓がないから法事ができない」は誤解
以下、順に見ていきましょう。
心の区切りとして有効
法事とはあくまで宗教的・文化的な慣習として行われるものです。
そのため必ずしも法事を行わなければならないわけではありません。
しかし、法事を行うことによって親族が集まり故人を偲び、心の整理をする機会となるのも事実です。
特に四十九日や一周忌、三回忌などの節目は、ご遺族にとって大きな意味を持つことが多いため、散骨後もこうした儀式を取り入れるケースが増えています。
「お墓がないから法事ができない」は誤解
法事は「お墓のある場所で行うもの」と思われがちですが、それは誤解です。
実際には、自宅や会館、お寺、などで柔軟なスタイルで法事を行うことができます。
法事において最も大切なのは、「どこで行うか」ではなく、「どのような気持ちで供養するか」です。
お墓がなくても、僧侶による読経や故人の遺影を囲んだ会食、献花などを通じて、十分に想いを込めた法事を行うことができます。
海洋散骨後に行われる主な法事・供養スタイル

海洋散骨後でも、故人を偲ぶための法事や供養は、さまざまな形で行うことができます。
散骨をしたからといって供養が省略されるわけではなく、むしろ形式にとらわれない自由なスタイルで、心のこもった法事を行うご遺族が増えています。
従来の仏教的なスタイルを踏襲することもあれば、家族のライフスタイルに合わせた新しい供養のかたちを選ぶ方も少なくありません。
ここでは、次の3つの代表的な法事・供養のスタイルを紹介します。
- 散骨当日に法要を組み合わせるケース
- 一周忌・三回忌など節目で行うケース
- 僧侶派遣付きの散骨などで行うケース
以下で、詳しく見ていきましょう。
散骨当日に法事を組み合わせるケース
海洋散骨当日に、法事を合わせて行うスタイルは、儀式をシンプルにまとめたい遺族に人気の方法です。
散骨後に、貸し会場などで会食をしながら故人を偲ぶ場を設けることが一般的です。
たとえば、海上で花をまきながら僧侶が読経をし、遺族が手を合わせるという方法も可能です。
また、散骨後の食事会では、故人の思い出話を語り合ったり、好きだった料理を囲んだりと、形式よりも想いを大切にした時間になります。
このように、散骨そのものを「法事の一環」と捉えて、自然な流れを組み合わせることで、無理なく、気持ちにも区切りをつけやすくなります。
一周忌・三回忌など節目で行うケース
海洋散骨後であっても、仏教における大切な節目である一周忌、三回忌などに合わせて法事を行うことは可能です。
これらの法事は、故人の霊を弔い、冥福を祈るための区切りの行事であり、家族や親族にとっても再会の機会となります。
遺骨が手元になくても、遺影やお位牌、思い出の品を用いて供養の場を整えることは可能です。
お墓がないから法事ができないと思う必要はなく、祭壇の前で祈りを捧げるだけでも、十分に心を込めた供養となります。
宗派や地域の慣習にもよりますが、散骨後でも仏教的な年忌法要を丁寧に行うことは、心の整理や親族間の絆を深める意味でも大きな意義があります。
これらの現代的な供養方法は、それぞれの家庭の事情や価値観に合わせて選ぶことができ、こうしなければならないという制約を受けない点が魅力です。
法事の本質は、形式ではなく、故人を想う気持ちにあります。
自分たちにとって無理のない、心のこもったスタイルを選ぶことが、何よりも大切です。
海洋散骨後の法事の場所・形式はどう選ぶ?

引用元:みらい散骨「東京湾代行散骨」
法事を行う場所や形式に明確なルールはなく、大切なのは、家族の希望や宗教観、故人の意志に沿った形を選ぶことです。
海洋散骨後の法事のやり方として、次の3つの方法があります。
- 自宅・寺院・会館などで行う
- 海にゆかりのある場所で行う
- 宗派ごとの作法に則って行う
以下で、それぞれについて見ていきましょう。
自宅・寺院・会館などで行う
一般的な法事の場所は、自宅、菩提寺、または法事会館などです。
自宅であれば、祭壇や遺影を用意して、親しい親族だけで落ち着いた時間を過ごすことができます。
寺院では正式な読経や法話を受けられる安心感があり、会館では人数に応じた会食の手配もしやすいのが特長です。
海にゆかりのある場所で行う
故人が海を愛していた、あるいは散骨を行った海に思い入れがあるという場合には、海辺での法事も選択肢となります。
たとえば、海が見える公園や施設の一室を借りて、親族で静かに手を合わせる場を持つというスタイルです。
神奈川県三浦市の海辺公園や、千葉県館山市の海が望める会場などを利用する例があります(公園を使用する際には、事前に管理者の許可を得る必要があります)。
また、散骨を実施した海域を再訪して献花や献酒を行うことで、海とのつながりを大切にした供養ができます。
宗派ごとの作法に則って行う
仏教の宗派によっては、法事の回数や内容、供養の作法に違いがあります。
たとえば、浄土宗では念仏を中心にした法要が行われ、真言宗では読経に加えて密教儀礼が加わることもあります。
そのため、可能であれば生前から付き合いのある寺院や僧侶に相談し、宗派に合った方法で法事を進めましょう。
宗教にこだわらない場合は、無宗教形式や自由葬スタイルも柔軟に選べます。
海洋散骨後に法事を行う際の注意点

法事は親族間の意向や形式の違いによってトラブルの元になることがあります。
さらに費用面でも想定と異なる場合があるため、海洋散骨後の法事については、次の点に注意するようにしましょう。
- 法事の時期や内容は親族の意向とすり合わせる
- 事前に寺院・僧侶などとよく確認を行う
以下で、詳しく見ていきましょう。
法事の時期や内容は親族の意向とすり合わせる
「散骨したし、もう供養はしなくていい」という考えの人もいれば、「やはり四十九日や一周忌はやりたい」と思う人もいます。
親族間で法事に対する価値観に違いがある場合、十分な話し合いと合意形成が不可欠です。
特に兄弟姉妹や子どもたちの間で意見が分かれることもあるため、事前に「どのような供養をしたいか」「どの程度の規模で行うか」などを話し合っておくことが大切です。
事前に寺院・僧侶などとよく確認を行う
僧侶を招いて法事を行う場合には、早めに連絡を取り、日時・場所・費用などの確認をしておく必要があります。
たとえば、法事の費用、僧侶へのお礼(お布施)などについてです。
散骨後の法事にかかる費用は、僧侶へのお布施(一般的に3万~5万円程度)、会食費用、会場費などを含めて数万円程度が目安になります。
地域や宗派によって差があるため、事前に確認しておくと安心です。
また、海洋散骨を行ったことに対して賛否がある僧侶も存在するため、事前に散骨済みであることを伝えたうえで受け入れてくれるかどうか確認しましょう。
寺院によっては散骨者向けの供養プランを用意している場合もあるため相談してみましょう。
海洋散骨後の法事は家族にとって無理のないスタイルを選ぶことが大切

この記事では、散骨後の法事の必要性や具体的な供養方法、実施場所、注意点などをわかりやすく解説しました。
法事は家族の気持ちに折り合いをつける節目です。
故人とのつながりを確認し直す貴重な機会なので、海洋散骨という現代的な供養の形を選んだとしても、法事が行えないわけではありません。
近年では、宗派や慣習にとらわれない柔軟な法事スタイルが広がっており、自宅や会館での少人数法要、海を望む場所での献花、オンライン法要など、多様な選択肢があります。
しかしながら、親族間で価値観が異なる場合もあるため、事前の話し合いや専門家への相談を通じて無理のない形を探ることも重要です。
「みらい散骨」は葬儀社が提供している海洋散骨サービスで、海洋散骨後の法事までトータルでサポートすることができます。
海洋散骨後の法事プランや費用のお見積もりについては、「みらい散骨」のお問い合わせフォームから24時間お気軽にご相談いただけます。